
8月17日に、夏休みの企画として「一茶基礎講座 Q&A一茶さん」を開催しました。当館学芸員を講師に、「一茶さんのヘアスタイル」、「江戸の三大グルメと一茶さん」、「やせ蛙の句はどこで詠まれた?」など、様々な切り口から一茶さんを紹介しました。
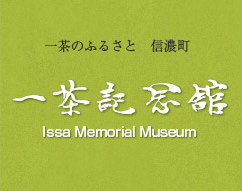

8月17日に、夏休みの企画として「一茶基礎講座 Q&A一茶さん」を開催しました。当館学芸員を講師に、「一茶さんのヘアスタイル」、「江戸の三大グルメと一茶さん」、「やせ蛙の句はどこで詠まれた?」など、様々な切り口から一茶さんを紹介しました。

7月20日、今年度の第2回一茶記念館講座を開催しました。今回は、テレビ・ラジオのコメンテーターとしてもおなじみの東京大学名誉教授月尾嘉男先生をお招きして「HAIKU!世界に飛躍せよ」と題してお話いただきました。
日本を代表する文化と言われている俳句ですが、俳句を趣味とする人の割合は全国民のたった2%程度と見積もられ、ほとんどの方が無関心。世間一般の方に広く趣味として定着しているとは言いがたいのが現状です。
一方で、世界各国では、世界でもっとも短い詩として、俳句がどんどん広がっていっています。現在国内では、俳句をユネスコ文化遺産に登録しようという協議会が設立され、運動を行っていますが(当信濃町も参加しています。)俳句を日本文化として世界に発信するために、このような状況でよいのかというのが今回のお話のテーマでした。
これまでも日本人は、浮世絵、建築、日本食など、様々な分野で自国の文化を大事にせず、外国から評価されて初めてその価値に気づくという、もったいないことを繰り返してきました。俳句もそうならないようにしたいものです。
また、俳句のように、物事を縮小して凝縮させるのは、盆栽、茶道、建築から、果ては戦後日本を牽引した工業製品に至るまで、日本人が古来から得意とするところであり、爆発的に資源を消費する物質文明の今後に、この能力は極めて重要な役割を果たすのではないかというお話もありました。


今回はTSUNAMIヴァイオリンコンサートを同時開催いたしました。TSUNAMIヴァイオリンは、東日本大震災で被災した木材を使用して製作されたヴァイオリンです。今回は製作者の中沢宗幸先生(写真上)からお話をお聞きするとともに、細川奈津子さん、川又慶子さんのお二人のヴァイオリニスト(写真下)に3曲演奏していただきました。
なお、本講演会開催に当たっては、長野市の美谷島健さんに仲介等大変ご尽力いただきました。この場をお借りし、改めて感謝申し上げます。

6月8日、記念すべき令和元年度の第1回一茶記念館講座を開催しました。今回は長野郷土史研究会会長の小林一郎氏に「父小林計一郎の一茶研究」と題してお話いただきました。
一郎氏の父である小林計一郎氏は、長野郷土史研究会を設立して初代会長となった方で、戦後の一茶研究をリードした研究者であるのみならず、善光寺の歴史や、真田一族、川中島合戦の研究など、郷土史のさまざまな分野で大きな業績をあげられました。
そのため、計一郎氏は歴史学者と認識されることが多いのですが、実際には高校の国語教師が本業でした。
計一郎氏が一茶研究へと向かうきっかけは大学時代に国文学者伊藤正雄に師事したことでした。伊藤正雄は明治以来諸家が積み上げてきた一茶研究を仔細漏らさず整理統合、集大成し、戦後一茶研究の出発点となった名著「小林一茶」(昭和17年 三省堂)を著した研究者であり、計一郎氏はその後継者という位置づけになります。
計一郎氏は、地方資料の活用や、統計的手法、筆跡研究など、それまでなかった新しい視点を一茶研究に持ち込み、様々な角度から一茶の実像に迫りました。また、計一郎氏の一茶への理解の根底には、家庭環境の相似と戦争体験があるというお話しもありました。
近代に入って正岡子規が一茶を特筆すべき俳人と評価し、研究が始まってからすでに120年。一茶研究自体が歴史を重ねるなかで、計一郎氏の業績は歴史の一ページとして輝いています。
子どもの日の5月5日は一茶さんの誕生日でもあります。
これを記念して、一茶記念館周辺では毎年一茶まつりと、全国小中学生俳句大会の表彰式が開催されています。
一茶まつりは今年で36回目。一茶音頭パレードや、様々な出店、催し物が開催されます。
当日はなんと一茶記念館入場無料です。
ゴールデンウィークにお越しの方はぜひお立ち寄りください。
一茶まつりについて詳しくは下記のページをご覧ください。
http://www.shinano-machi.com/event/2977
※なお、当日は駐車場が変更になりますので、会場周辺の係員の誘導に従って駐車をお願いします。
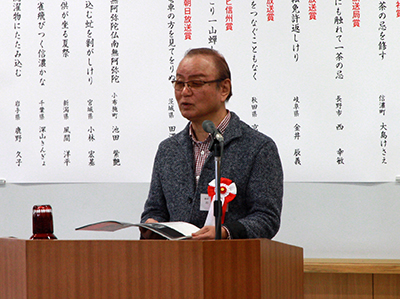
一茶の命日である11月19日に、恒例の一茶忌全国俳句大会が、一茶記念館を会場に開催されました。
午前中は、俳人で「炎環」主宰の石寒太先生の記念講演が開催されました。今回は、「ふるさとの一茶」と題して、ご自身一茶忌へのこれまでの関わりも含めて、一茶俳句の特色をおはなしいただきました。
お昼には、恒例の、地元の新そばを味わってもらうそば会が開催され、多くの人がおいしいそばに舌鼓を打ちました。

10月20日 俳人宮坂静生氏講演会

10月21日 研究発表(小林孔氏)

10月22日 文学散歩(中野市 山田家資料館)
10月20日から22日の3日間、俳文学会第70回全国大会が、一茶記念館を会場に開催され、全国の俳文学研究者が集まりました。
初日は、俳人宮坂静生氏による講演、2日目は学会員による研究発表、3日目は、信濃町、中野市、小布施町、高山村の一茶ゆかりの地をバスでめぐる文学散歩が行われました。
初日は少し雨が降りましたが、翌日以降天候にも恵まれ、色づき始めた紅葉を眺めながらの開催となりました。最新の研究に加え、一茶に関する大変興味深い研究発表もあり、一般の参加者の方にも非常に貴重な機会となりました。

9月15日、俳人で「古志」主宰の大谷弘至氏を講師にお迎えして、今年の第3回一茶記念館講座を開催しました。大谷さんは、著書もある一茶研究者であり、また今年からは、当館が主催する小林一茶全国小中学生俳句大会の選者もお勤めいただいています。
今回は「若き日の一茶」と題してご講演いただきました。現在確認される一茶のもっとも古い旅は寛政元年(1789)、一茶27歳のときの奥州への旅です。一茶はこの旅を「奥羽紀行」にまとめたとされますが、それは現在まで発見されておらず、どんな旅をしたかは不明のままです。恐らくは、松尾芭蕉の「奥の細道」の旅路をたどったのではないかと推測されているだけです。
しかし、歴史を紐解くと、少し違う様相が見えてきます。この旅のわずか6年前、東北地方は天明の大飢饉により数十万人に及ぶ餓死者を出しています。他の文献から、一茶が旅した頃は、その惨状の痕跡が未だ色濃く残っていたと推測されるのです。一茶は奥州の旅で、図らずもそうした悲劇のあとを目の当たりにしたのではないかと考えられます。
大谷さんは、若き日の一茶はこのときの経験から、災害に対する人間の無力さ、はかなさを強く意識するようになったのではないかと考えています。
こうした視点は、これまでの一茶研究にまったくないものです。今回は、こうしたお話を中心に、若き日の一茶の俳句の評価をお話いただきました。

7月28日、第2回一茶記念館講座を開催しました。今回は、一茶記念館で現在開催中の企画展「一茶365+1きりえ」の作者である柳沢京子さんをお招きし、企画展の元となった作品をどのように創作したかを中心に、一茶俳句と作品の関わりをご講演いただきました。
柳沢京子さんは、テレビ局の広告制作のお仕事から転身、きりえ作品を創作するようになり、代表作である「一茶かるた」を発表されました。その後、一茶の俳句が縁となり、ドイツ各地で個展を開催することとなりました。文化の全く異なるドイツの方々は、一茶の俳句だけでは情景が想像できないが、きりえ作品とともに鑑賞することで理解できるようになるということで、大変喜ばれたそうです。
また、作品に使用している紙は、江戸小紋の人間国宝小宮康孝氏から授かったもので、使用を熱心に勧めてくださった小宮氏には、大変深く感謝しているというお話もありました。

6月1日から開催中の企画展「一茶365+1きりえ~柳沢京子の世界~」の展示替えを行いました。展示品約30点のうち、20点弱を入れ替えましたので、是非ご覧ください。
今回の展示替えでは、地元信濃小中学校の8年生(中学2年生)1名がお手伝いをしてくれました。写真では、真剣な表情で、キャプション貼りを手伝ってくれています。

6月30日、今年度の第1回の一茶記念館講座を開催しました。今回は、一茶研究の第一人者である、上田市在住の矢羽勝幸先生を講師にお招きし、「一茶と二六庵」というテーマでお話いただきました。
青年期に江戸で俳諧の道を志した一茶は、「葛飾派」と呼ばれる流派に入門し、何人かの俳人に師事しましたが、そのうちの一人二六庵竹阿から、「二六庵」の庵号を継承し、「二六庵一茶」と名乗りました。
これまで、一茶が二六庵を名乗った時期は、寛政11年(1799)から享和元年(1801)の間とされてきましたが、昨年当館が発見した新資料により、享和3年まで名のり続けていたことが判りました。
一茶記念館ではこの新資料「一馬三回忌追善集」を矢羽先生に研究していただき、その成果を今回初めて発表していただきました。庵号は、俳諧宗匠(流派公認の俳諧の師匠格)の資格を示すものであり、一茶は俳諧宗匠として、この本が出た翌年、文化元年か、さらにその次の年まで活動していたと考えられます。
一茶はちょうどこの時期、葛飾派を離れ、夏目成美ら、当時の江戸の一流俳人との交流を活発に始めますが、一説には破門されたとされる葛飾派離脱の理由や、その時期などは、これまで様々な説が提唱され、定説がありませんでした。今回の講演では、新しい発見を元に、この問題に新たな光が当てられました。
今回の新資料は、講演後一茶記念館常設展示室で展示しております。よろしければ是非ご覧ください。